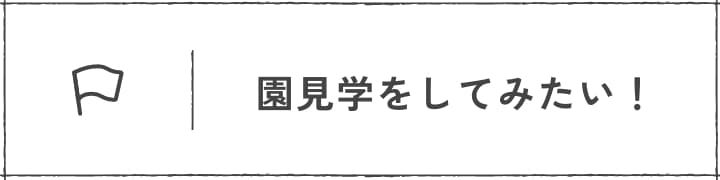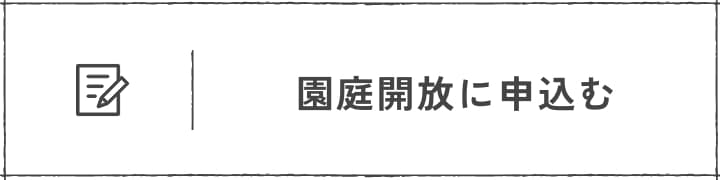お正月のあそび~七草~なわとびで寒さに負けない体づくり
1月6日 お仕事が始まる方も増えてほとんどの子が元気に登園してくれました。
新年の挨拶を保護者の方や保育士がしているのを見て真似る子ども達でしたが、
大きいクラスのお友達になると自分から
「あけましておめでとうございます ことしもよろしくおねがいします」
とご挨拶をしてくれる子どももいました。
日本のお正月にする昔ながらのあそびを子ども達にも伝えていきたいという事で
お正月あそびを用意してくれました。
まず、「 あけましておめでとう 」童心社 の絵本を読み、
お正月クイズを楽しんだあとにあそびの紹介です。
子ども達が紙皿に切ったり書いたりした物を保育士が組み立てましたが
「う~んうまくいかない~」と悩みながら作っていた
ジャグリングです。
クルクル回る様子をみて子ども達は目を丸くしながら
「うわぁ~」と声をあげていました。

風船羽子板・こままわし・お手玉・けんだま
他にも福笑いやカードあそび・・・
盛りだくさんです。
しばらくお正月のあそびを各クラス楽しみます。

1月7日は七草がゆの日
「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ
すずな・すずしろ」
これぞ七草!と小さい頃覚えた記憶があります。
健康を願って、7種の野草が入ったかゆを食べる。
お正月に食べ疲れた胃腸を休めるという知恵もふくまれている
ようですね。
野草に芽を出す七草には、ビタミンなどの栄養がたくさん入っているようです。
それぞれの草にも色々な意味があるようなのでご紹介致します。
せり・・・若葉が伸びる様子が競い合っているように見えることから名がつけられた
なずな・・・撫でて汚れを取り除くという意味があると言われています
ごぎょう・・・ごぎょうとは人型のこと。仏の体を意味すると言われています
はこべら・・・茎に葉がたくさん付いている様子から繁栄を意味します
ほとけのざ・・・葉の付き方が仏様の蓮座に似ていることからそう呼ばれます
すずな・・・かぶの古い呼び名で、神を呼ぶ鈴を意味します
すずしろ・・・大根のことでその色から潔白を意味すると言われています
今日のおやつに七草がゆがでます。
七草を食べて、今年もみんなが健康に過ごせるように願いたいです。

お部屋でのあそびも楽しいのですが、大きいクラスのお友達は
このお正月の間に
「なわとびが跳べるようになった!!」
と話してくれる子どもも何人かいました。
寒さに負けず外で遊んでいたのですね。
なぜなわとびを頑張っていたかと言うと・・・

目標に向けてチャレンジし、合格すると体育指導の先生が
なわとびにシールをはってくれます。
それが嬉しくて寒さに負けず子ども達はなわとびを
頑張るようです。