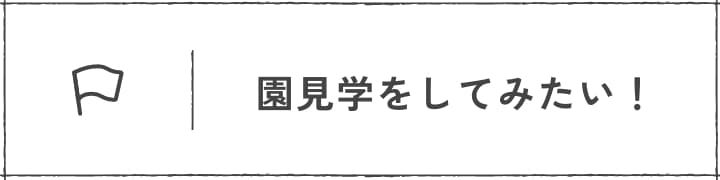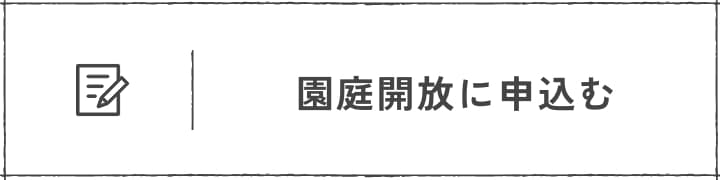おもちつきを楽しみました!!~園庭開放~
園庭で、おもちつきを行いました。
おもちつきを間近で見る機会も少ないので、子どもたちは珍しそうに眺めていました。
厨房の先生方が道具を見せてくれて・・・
「これはなにかな?」と聞いてもなかなか返事はかえって来ず、
「臼(うす)」「杵(きね)」と言うんだよと教えて頂きました。
まず臼をお湯で温めて・・・蒸し上がったもち米が入れられると
ぎゅっぎゅっともち米をつぶす作業に力が入ります。

蒸し上がったもち米は何ともいい匂いがして、子どもたちも香がしてもらうと
ぱあ~と目を輝かせて嬉しそうでした。

おもちつきの由来はどういうものなのでしょうか?
日本には稲作信仰というものがあり、稲は「稲魂」や「穀霊」が宿った神聖なものだと考え、
崇められてきました。
稲から採れる米は人々の生命力を強める神聖な食べ物であり、
米をついて固める餅や、
米から醸造される酒はとりわけ力が高いとされています。
そこで、祝い事や特別な日であるハレの日に、餅つきをするようになりました。
餅つきは一人ではできないため、皆の連帯感を高め、
喜びを分かち合うという社会的意義もあります。
そして、お正月には「鏡餅」、桃の節句には「菱餅」、端午の節句には「柏餅」というように、
行事食としても定着していきました。
とりわけ日本の行事文化の大黒柱であるお正月はお餅が重要な役割を果たすので、
年末に餅つきをするようになったそうです。
一緒におもちつきを楽しむために地域の方も来てくださいました。

5歳児と保育者がもち米をぺったんぺったんと突き上げてくれて、
おもちが出来上がりました!!
さあ、ころころ丸めるみんなの出番です。
待っていました!!とばかりに子どもたちは
頑張って丸めてくれましたが、しわが入らないように
つるつるのおもちを作るのはなかなか難しく苦戦していましたが
楽しんでくれていました。

小さいクラスのお友達もつき上がったおもちの温かさに触れ、
興味津々でした。

4・5歳児がLaQで作った鏡餅にのせる葉付きみかんを乗せると鏡餅の完成です!
※本来鏡餅にのせる果物は 橙(だいだい)です。
橙は収穫せずそのまま置いておくと、なかなか木から落ちない(長ければ2~3年)
代用するみかんが葉付きなのは、
鏡餅の上に橙を置くためには木から外さないといけない
でも「なかなか木から落ちない=縁起物」という意味があり
そこで少しでも木になったままの状態を維持するために葉付きのままにしてるそうです。
だいだい(橙)色で、子孫が代々(だいだい)まで繁栄するようにということで縁起を担ぎ、
お餅を重ねるのは「穏やかに年を重ねる」という意味で、大小のお餅で太陽と月を表現している
という説もあるそうです。
日本の伝統を知り、穏やかに年を重ねるために鏡餅をお家にも飾ってみませんか?

次回は、クリスマス会の様子をお伝えします。